戦争記憶の伝承は、かくも難しい。映画「長崎の郵便配達」。
ピーター・タウンゼンドと聞いて「who?」と思う人も、「who!」と思う人もいるでしょうが、
The Whoのギター弾きながらジャンプする人ではありません。
第二次世界大戦の英国パイロットとして英雄になり、
英王室とのロマンスで「ローマの休日」のモチーフともなったとも言われる人らしいです。
戦後は、ジャーナリスト&作家として活躍され、
英雄軍人から一転して、戦争被害者となった子どもたちに注目するようになった人です。
その取材の一環として、彼は16歳で郵便局員として長崎で働いてるときに被爆して、
凄まじい火傷を負いながら生き延びた谷口稜曄(スミテル)さんと出会い、
彼のことを書いたノンフィクション小説「THE POSTMAN OF NAGASAKI」を出版します。
今では、ピーター・タウンゼンドさんも谷口稜曄さんも故人ですが、
ピーター・タウンゼンドさんの娘さんが、父の足跡を追うようにして、
谷口さんを通じて、長崎の原爆被害に迫る映画が「長崎の郵便配達」です。
娘さんの言葉を通して、父への愛惜も交えながら、
少し情緒的に美しく描いてるので、
よけい、原爆の悲惨さが強調されます。
ピーター・タウンゼンドさんが残した膨大な取材カセットテープから、
ピーターさんや谷口さんの、今まで公開されてない肉声が聞こえてきます。
歴史的資料としても価値ある映画なのかもしれません。
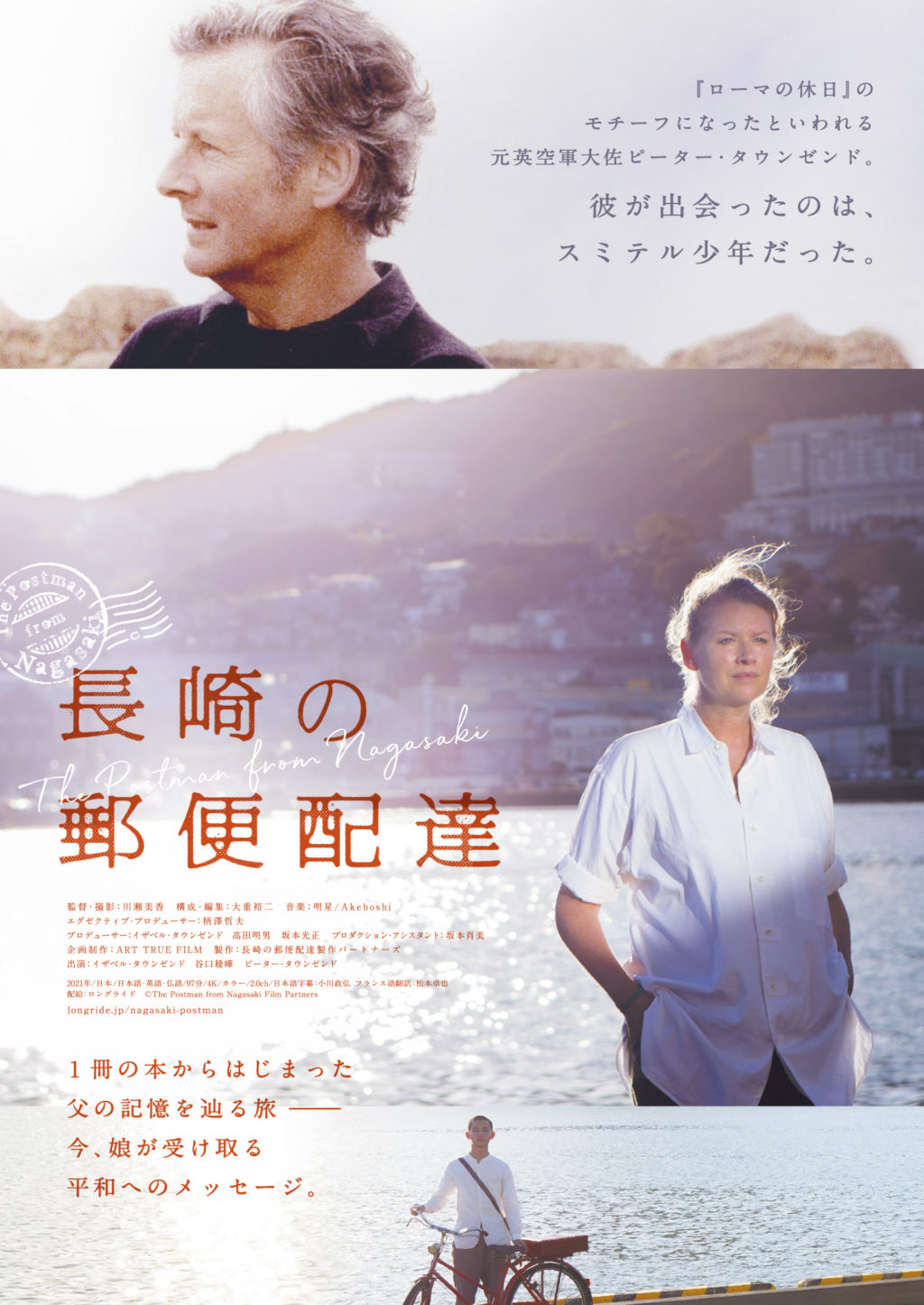
ただ、当事者ではないピーターさんの娘さんと監督の川瀬美香さんの目を通して語られるので、
少し、現場が遠く感じてしまったりはします。
情緒的な映像から、そんな気持ちになる部分もあるのかな?
そして、やはり谷口さんの証言以上の新事実が出てきてないのもあって、
どこか遠くから眺めてるような気分になるところもあります。
観てて「なんかグサッと来るところが少ないんよなあ」と思ったのですが、
ふと「伝承の難しさ」ということを思いました。
沖縄でも、今や本物の沖縄戦を体験した人が少なくなってきて、
戦争体験の伝承が、大きな曲がり角に来てる印象がありますが、
それと同じことが、この映画にも言えるのかもしれない。
こんだけ良くできていて、新資料(ピーターさんの取材カセットテープ)があっても、
そんな印象を抱いてしまうのか。
これから、戦争体験を次の世代に伝えていくことは、
より難しくなってくるでしょうけど、
なんとか、あのような戦争を繰り返さないために、
リアルな悲惨さを、伝える方法を考えないとあかん時期に来てるんやないかな、
思いました。

