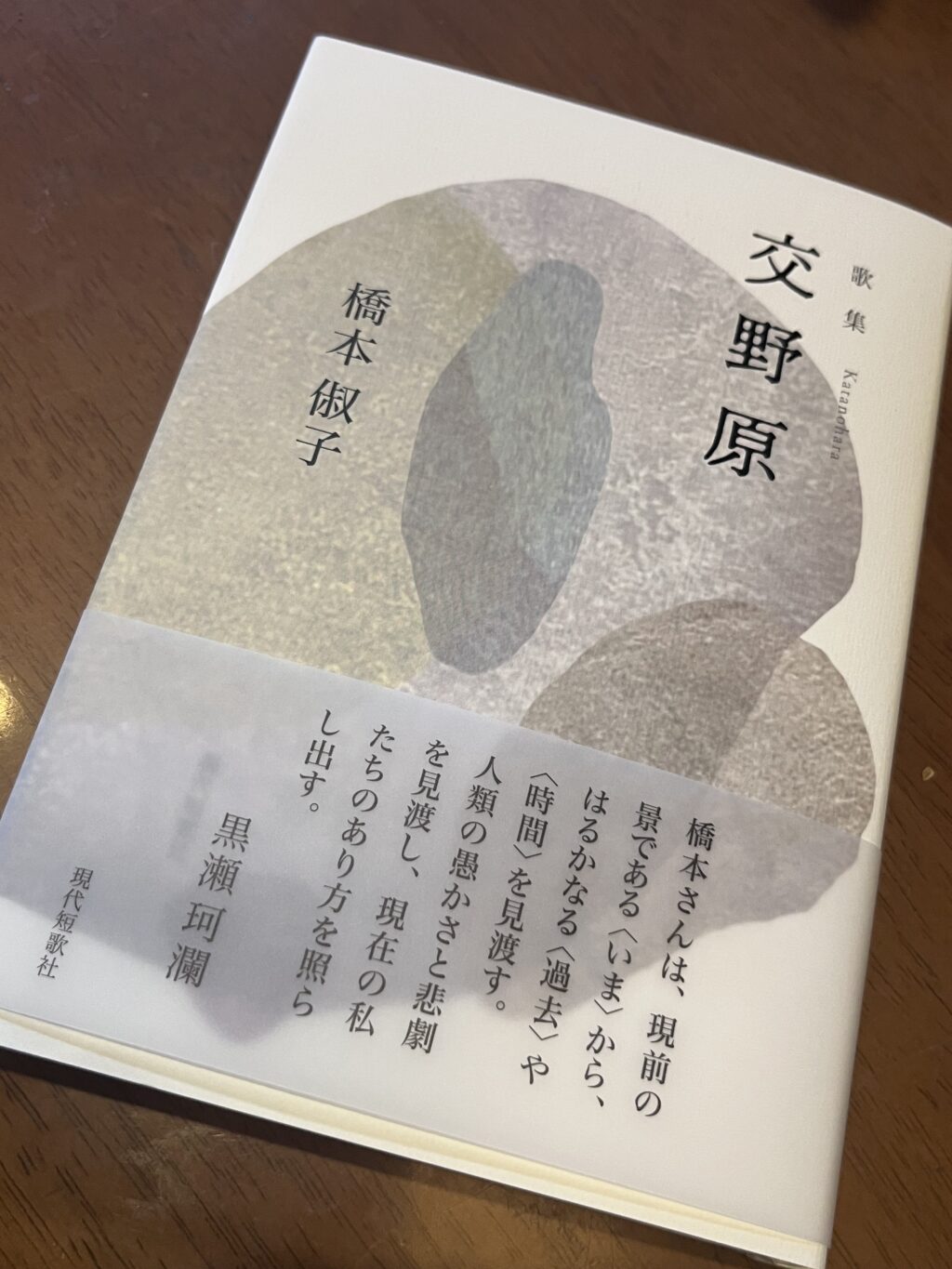第69回日本伝統工芸展@大阪髙島屋。
終ってしまった展覧会の話で申し訳ないのですが、
先日、毎年行ってる「日本伝統工芸展」に行って来ました。

何れ劣らぬ名品揃いで、新作ばかりなので、
日頃、古い名品をよく観てる目には、
新鮮で、すごく色鮮やかに思えました。
けど、ちょっと気になったのは、どの受賞作も、
彩色は大胆でも、造形が幾何学的で繊細なものばかりでした。
そういうのがあかんとは、もちろん申しませんが、
ほぼ全部がそういう傾向なんて、
どうなんやろう、と、少し思いました。
日本伝統の侘び寂びとか、少し不完全なものを美しいと感じる観点が
抜けてるような気がしました。
ワシ自身、アシンメトリーなものとか、
ちょいとひしゃげたものとかが好きなので、
あまりに完全なものなかりで少し息苦しく感じました。
「なんだか美術というより、技術の競い合いみたいやなあ」と思いました。
たぶん、技術があった上で、そういう不完全なものを創るのは、
完全なものを創る以上に難しく、センスもいるんやと思いますが、
個人的には、そういうのも、創ってほしいし、
それを評価してほしい、と思いました。
その中で一番印象に残ったのは、
入口の看板にも載ってた満丸正人さんの『木芯桐塑布和紙貼「夕浜」』でした。

戦前の沖縄の漁師さん(ウミンチュ)がモチーフらしいのですが、
太くて逞しい足に、この漁師さんが生きて来た時間を感じ、
少し乱れた着物の裾に、夕方の気持ちいい風を感じ、
満ち足りた表情に漁の成果を感じました。
きっと、生きている人間らしさを、
この展覧会の中で、一番感じたんやと思います。
振り返ってみると、そのほかのきっちりとした造形の作品って、
そういう人間味みたいなものが、
少し感じにくいのかなあ、
だから、この作品が一番残ったのかもなあ、
とも思いました。
知り合いの阿部遼さんは、今年も受賞されてたのですが、
受賞作は、大阪では展示がなかったようです。
残念!
来年の日本伝統工芸展も楽しみです。